経営方針
経営トップ×社外取締役 対談
中期経営計画4年間で実現した「進化」と次の成長に向けて
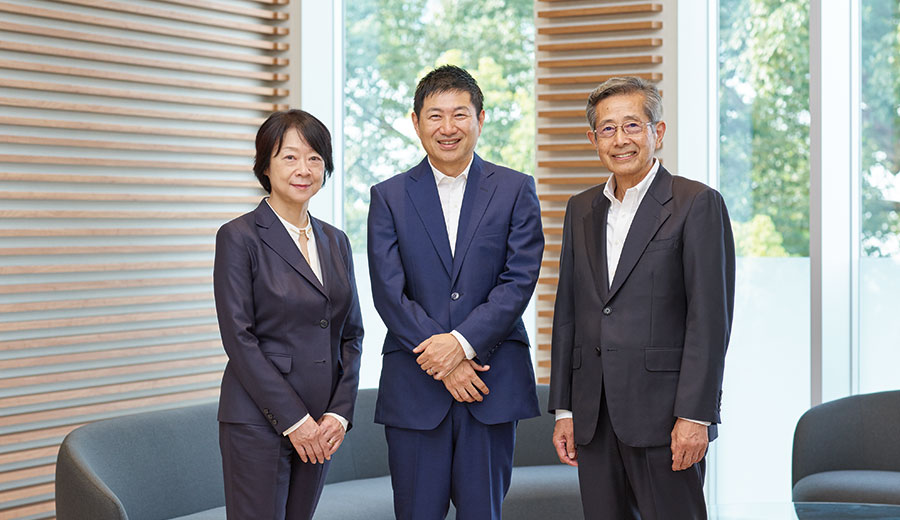
中期経営計画2023「進化への挑戦」はいよいよ最終年度へ。コロナ禍や地政学的リスクなど、グローバル規模で大きな社会的混乱に見舞われたこれまでの4年間、デクセリアルズはどのように進化し成長してきたのか。そして次なる成長に向けた課題や新たに取り組むべきこととは。現中期経営計画の軌跡をよく知る取締役3氏が4年間を振り返り、将来に向けた展望を語り合いました。

代表取締役社長
新家 由久

社外取締役(指名・報酬委員長)
横倉 隆

社外取締役(監査等委員長)
佐藤 りか
社会環境の変化

新家いよいよ最終年度に入った中期経営計画2023「進化への挑戦」(以下、中計)は、2019年よりスタートしました。この中計が始まってすぐに外部環境が急速に、大きく変化したことで、先行き不透明な時代に突入したことを強く感じながらの歩み出しになりました。
当時、米中貿易摩擦が激化し、両国のデカップリングの動きも顕著になり始めた時期でした。そして、コロナ禍やロシアによる突然のウクライナ侵攻など、まったく予測しえなかった大きな社会的混乱が起きました。
その一方で、SDGsを始めとするさまざまな社会課題にしっかり向き合う意識が広まり、ものごとをどう効率的に進めるか、いかにデジタル技術を活用してより良い社会をつくるかという機運も高まりました。それがこの4年間における社会の大きな変化でした。
横倉確かにDXや生成AIなどのデジタルテクノロジーが社会の高度化をけん引するという意識が急速に広がりました。また、企業のあり方について、証券取引所や中央官庁から、意見が発せられることが以前に比べて多くなりました。これにより、各企業がサステナビリティや企業価値の向上をより強く意識する流れが生まれたのも大きな変化だったと思います。
佐藤コロナ禍で、リモートワークを含めデジタル化が一段と進んだのは、多くの方々が実感する社会的な変化でした。私が携わる法律の世界でも、裁判手続きのデジタル化が進むなど、新たな動きが生まれています。
こうした仕組み上のデジタル化が進むと同時に、人と人、そして社会と人とのつながり方について、新しいコミュニケーションスタイルを模索する動きが深まったのも非常に大きな変化だと感じます。
横倉以前もITバブルの崩壊やリーマンショック、そして東日本大震災の発生と、数年の間に予想外の出来事が次々に起こりました。一度大きな混乱が起きると、元に戻るまで数年かかるのですが、それらの事象が立て続けに起こりました。
― そして、この4年間でのコロナ禍やウクライナ問題。この先も想定外の社会的混乱は頻繁に起きると想定すると、リスクマネジメントだけでなく、レジリエンス(回復力)を高めることが重要になると考えています。
中期経営計画で挑戦してきた4年間での「進化」
新家現行の中計で定めたのが、①新規領域での事業成長加速、②既存領域における事業の質的転換、③経営基盤の強化という3つの基本方針です。
この4年間で既存領域の事業を磨き上げ、新規領域にリソースを集中投下したことで、事業ポートフォリオの転換が大きく進展しました。また、それを支える経営基盤の強化についても、現場と経営を一体化し、よりスピーディな経営判断を実現するための栃木への本社移転、監査等委員会設置会社への機関設計の変更、リモートワークや「ジョブ型人事制度」の導入、国内社員への自社株式給付など、成長に向けた数多くの施策を着実に推進することができました。

横倉今回の中計で、特に経営基盤強化はしっかり進んだと感じます。私は前中計の時からデクセリアルズを見てきましたが、前回は「構造改革」が大きなテーマで、会社が新しくデクセリアルズとして立ち上がり、足元の経営基盤の確立に力を注ぐものでした。そして今回の中計では、一定程度整った経営基盤を強化するステップに移り、会社に力強さが加わるとともに、社内がより活性化したと実感しています。
また、新規領域への進出と既存領域の見直しによる事業ポートフォリオの転換も大きく進展したと評価しています。社会やお客さまのニーズを先回りした商品開発がマーケットにマッチし、収益性の高い事業活動が行えるようになりました。
佐藤私は取締役会での議論や執行サイドの取り組みが課題を先取りし、その実現を常に意識するようになったことが、事業ポートフォリオの転換などの、より良い結果に結びついたと実感しています。そして何より今回の中計での最大の成果は、数々の数値目標を着実に達成してきたことです。
横倉加えて、外部からの人財も積極的に加えつつ経営体制の強化を実現してきたことも、次の成長につながる大きな成果です。社長を始めとする執行サイドの方々にとっては、この4年間の成長に対し、相当な苦労や努力があったと推察します。
新家2019年に現在の経営体制に移行する際、自分たちは変わらなければいけないという危機感を強く持っていました。そして、まずは経営層から変えていくべきだと考え、外部人財の探索と登用を積極的に行いつつ、社内の最高意思決定機関としての取締役会の形も変えました。
その過程で、変化に対して、どのようなスキルを持つ人財が必要なのかを考えて続けてきました。内部で登用すべき人もいましたが、社内に足りないスキルは、それを備えた外部の方に加わっていただくことが必要だったのです。
もともと当社は、中途入社の社員が多い会社です。管理職層の半数ほどをそれらの人財が占め、それらの多様なバックグラウンドを持った方々が成長の原動力になってきたところがあります。
4年間の印象に残る取り組み
新家現在の中計が始まって以来、さまざまな改革や施策を、スピードを上げて実行してきましたので、私としてはあっという間の4年間でした。
数々の施策のなかで、特に印象に残る取り組みを教えてください。

佐藤私自身が深く関わったこともありますが、機関設計を監査等委員会設置会社へ移行したことは特に印象に残る改革です。本質的な部分で、この改革がもたらした最も重要なポイントは、執行サイドへの権限委譲が大幅に進展したことです。この移行により、各現場でより一層スピード感を持った対応ができるようになったはずです。
また、取締役会での議論の中心が「デクセリアルズはどうあるべきか」という、より本質的で密度の高いものになってきたことに、この4年間の進化を感じています。
横倉私が特に印象深いと考えているのは、2022年の(株)京都セミコンダクター(以下、京セミ)のM&Aです。当社は以前から外部の企業に出資や投資をしてきましたが、今回はそれらよりもずっと規模の大きな事案でした。当然、M&Aに至るまで取締役会でさまざまな議論を重ねてきましたが、最後に社長が、「自らが京セミをけん引し、先頭に立って旗を振っていく」と仰られました。この時、今回のM&Aを「社長自らの責任でデクセリアルズの将来の成長につなげていくのだ」という経営トップとしての強い意志を実感し、私は納得感を持ち賛成しました。
ただ、M&Aによるシナジー効果はすぐに生まれるものではありません。足し算はすぐにできても、そこから先のプラスアルファの成果が生まれるまでには、一定の時間、辛抱強く見守る必要があると考えています。
新家京セミのM&Aでは、取締役会で私たちが目指す会社のイメージを明確に持ちつつ、「なぜ、京セミを仲間に迎え入れたいのか」という議論を深めてきました。
社外取締役の方々の理解が、最終決断をするための心強い力になりました。
取締役会の進化
新家現在の取締役会構成メンバーに変わり、まずは互いの信頼関係の構築が大切であると考え、取締役会という意思決定中心の会合だけでなく、「オフサイトミーティング」などのさまざまなアジェンダについて議論する機会を設けました。時には「合宿」のような形で、社外取締役の方々とさまざまな経営課題を話し合ってきたことで、相互理解と信頼関係が深まったと感じています。
横倉定期的に行っている「独立取締役の会合」も、大変良い取り組みです。それぞれの観点から、疑念点や課題感を自由に発言しつつ、率直な意見を交わし、必要に応じて執行サイドにも対応をお願いしています。
また、私を含む、監査等委員会メンバー以外の社外取締役が監査資料を閲覧できるようになったことも、非常に実効性が上がる取り組みです。監査資料を通じ、社内の風土や文化、現場でのリアルな出来事など、細かな気づきを得ることが少なくありません。飾らない情報が得られることは、私にとっての安心感につながっています。
独立取締役と監査等委員の取締役の方々との意見交換の機会も設けていただいており、そこで得られる情報も少なくありません。

佐藤監査等委員長として、すべての取締役の方々に役立つ情報や資料を可能な限り幅広く共有しようと努めてきたので、大変うれしいです。
監査等委員のメンバーは、社内の方々からさまざまな説明を受けるため、監査等委員以外の社外取締役に比べて入手できる情報が多く、かねてから情報格差の解消に課題感を持っていました。すべてを開示するわけにはいかないものの、取締役間の情報共有には意識的に取り組んでおり、その成果が出ていることに安心しました。
一方で、社外取締役として活動するなかで、執行サイドの方々が率先して私たちの理解を深めようと努力されているのも感じています。例えば京セミのM&Aでは、同社の事業所視察を企画いただき、その後に合宿のような形で皆さんと新たな角度での議論ができました。
「現地現物」で初めてわかることもあり、その大切さを改めて実感しました。
横倉会社に対する理解を深め、取締役間の信頼が厚くなっているのと同時に、時にはけん制し合う緊張感が保たれているのは、現在の取締役会の良い点です。
私は、常にさまざまなステークホルダーの存在を思い浮かべ、健全な経営ができているかを厳しく見ることを意識して取締役会に関わっています。
佐藤確かに取締役会には緊張感があります。京セミのM&Aの際も、ネガティブな意見や指摘を含め、率直かつ活発な議論ができました。
新家私も取締役会を、ただ仲の良いメンバーの集まりにしようとは考えていません。社外取締役の方々には、それぞれ異なるバックグラウンドがあり、多様なご意見から気づかされることが多々あります。共通の目標は会社を持続的に成長させることであり、執行サイドの提案に対し、さまざまな角度からサジェスチョンをいただくことは非常に大切なことだと考えています。
取締役会を建設的な議論を交わす場にするよう意識してきましたが、それもこの4年間で大きく進化したことの一つだと感じます。
事業における今後の展望と課題
新家いよいよ2024年度からは新たな中計に移ります。
次期中計は、経営環境は今後も大きく変化し続けることを前提として策定する必要があります。取締役会の方々とは目下、今後の先行きが不透明ななか、どのようなリスクと機会が想定できるかを議論し、そのうえでどのような進化が遂げられるのか、遂げるべきなのかを探っているところです。
現中計では、自動車事業の拡大やフォトニクスなどの新たな方向性が見え、事業ポートフォリオの転換は大幅に進みました。しかし今後の成長に向けては、もっとダイナミックに変化する必要があります。
佐藤これまでのさまざまな施策により、デクセリアルズの既存領域には確固たるものができてきたととらえています。そこをしっかり維持しつつ、さらに深掘りする。同時に新規領域の展開が今後の成長のポイントになるのは間違いなく、より一層、加速させる必要があります。そして、それらを投資家など社外の方々に対し、いかに示せるかがより重要になると考えています。
当社の製品は接着剤から光半導体まで多岐にわたり、社外取締役とはいえ専門外の私にはわかりにくいこともあります。製品のことも含め、ステークホルダーの方々に、デクセリアルズをもっと知ってもらうための情報発信を続けることが必要です。
新家ステークホルダーとのコミュニケーションは大変重要です。当社をより多くの方に、より深く知っていただくための活動や工夫も、一層、活発化していきたいと考えています。
また、新規ビジネスの展開については、当社の連結子会社であるDexerials Precision Components(株)と京セミの事業およびリソースを統合した新会社の発足準備を開始するなど、すでに動き始めています。両社は2024年4月に統合予定であり、この統合会社をフォトニクス事業の成長をリードする存在にしていきたいと考えています。

横倉私が近年強く感じるのは、技術革新のスピードがグローバルベースで格段に速くなっていることです。生成AIなど、日々新しい技術が生まれています。
過去にも「技術革新の時代だ」と何度も言われたことがありましたが、現在のようにデジタル技術の活用によって材料の分野でも日々革新が起きるほどではありませんでした。
そうした状況にあって私が申し上げたいのは、どれほど新しい技術でもグローバルベースでは同じようなことを考えている人は大勢いるし、すでに誰かが手掛けているかもしれない。
そこで重要になるのは、技術を司る「人」です。優れた人財に集まってもらえる仕組みと、最大限の活躍をしてもらえる環境づくりは、今後ますます重要な経営課題になると思います。
さらなる成長に向け、より重要になる人的資本の強化

新家私も当社の強みであるビジネスモデルの強化を実現するカギは、「人」であると認識しています。外部の優秀な人財に当社を選んでいただき、活躍してもらえる企業になることは大変重要です。
そのための改革の一環としてまずは2023年度より、国内の管理職を対象として「ジョブ型人事制度」を導入しました。マクロで見ると日本の労働生産人口が減少していくのは確実です。当社の事業ポートフォリオも、よりグローバル目線で変えていきますし、人財のポートフォリオもグローバルレベルでの見直しを進めていきます。そのため世界中で優秀な人財が活躍できるよう、「ジョブ型人事制度」のグローバル展開についても着実に行っていきます。
横倉少々話がそれるかもしれませんが、社長はよく「私たちはベンチャー企業だ」とお話しされます。確かに創業10年の若い会社です。とはいえ、経営基盤もどんどん進化し、取締役会も変化している、大きな上場会社です。社長がおっしゃる「ベンチャー企業」にはどのような意味が込められているのでしょうか。
新家さまざまな意味を含んでいますが、先ほどのお話にもあったように、世の中の技術革新のスピードは非常に速く、今までなかったもの、世界の価値になるものを生み出していくためには、常に新しいことに挑戦する意気込みが欠かせません。
東証プライム市場に上場はしていますが、スタートアップ企業と同程度の気概で事業に取り組むことがデクセリアルズらしいと考え、「ベンチャー企業」という言葉を使っています。「ベンチャー企業」のように若い人でも意見を言いやすく、チャレンジしやすい風土の会社であり続けたいという気持ちもあります。
横倉飽くなき挑戦ですね。私もリスクテイクをしっかり行いつつ、より一層、懸命に後押ししたいと思います。
ステークホルダーの皆さまへのメッセージ
横倉デクセリアルズの強みであり、持続的な成長の源泉となっているのは、ニーズを先回りし、お客さまの期待を上回る製品をお届けする力であると私は思っています。それが現在の業績につながっており、社員の皆さんの自信にも結びついているはずです。
当社の事業の中心はデジタル分野であり、今後も社会から必要とされ続ける分野であるのは間違いありません。しかしながら、かつて「ITバブル崩壊」が起きたように、業界内での波はあります。
そうした外部環境に左右されない、強固な企業体質の構築にも取り組んでおり、徐々に結果も出てきました。自動車向けや通信、センシングなど製品領域を広げることで、環境の変化に柔軟に対応できる体質になってきました。ただ、まだまだ足りない部分もありますが、飽くなき挑戦を続けるのがデクセリアルズです。
社外取締役の一人として、持続的な成長とさらなる企業価値向上の実現に向け、あらゆるステークホルダーを意識しつつ、健全な経営が続くよう助言や提言を行い、最大限のサポートを行っていきます。
佐藤創業からの10年を振り返ると、立ち上がりには困難な時期もあったものの、その後しっかり飛躍を遂げ、良い形で10年の区切りを迎えることができたと感じています。
この先の10年は、当社が培ってきた技術をさらに磨き、やる気に溢れ、柔軟性を備えた人財に集まってもらう。そして能力が十分発揮できる環境を整え、経営陣もそうした人たちをしっかり引き上げ、より一層、社員と経営陣の良好な関係性を築いていただきたい。それは持続的に成長するために必須です。
私は監査等委員長として、自分たちの活動が会社のビジネスにどのように貢献できるのかを常に考え続けてきました。社内のガバナンスやコンプライアンスの体制がしっかり確保できていればこそ、会社は事業に集中できるはずです。監査等委員会は特にそういう面で貢献できていると感じています。また、監査等委員会の下に内部監査部門を置いており、執行サイドの懸念や課題をいかに適切に汲み取るかも意識してきました。
これからも取締役会や執行サイドとのコミュニケーションを積極的に行い、より一層の発展と成長に寄与する監査活動を進めていきたいと考えています。
新家次の10年に向けてどのような企業に成長すべきかというお話、まったくその通りだと感じます。
これまでの10年は、ソニーグループからの独立でスタートし、それ以前の50年の基盤を活かしつつデクセリアルズという新たな会社をどう成長させていくか、試行錯誤を続けた10年でした。そのなかでもこの4年間は進化が加速し、自信にもつながりました。
今後さらに多くの株主・投資家、お客さま、そして優秀な人財から選ばれ、応援していただける企業になるよう努力を続けてまいります。

